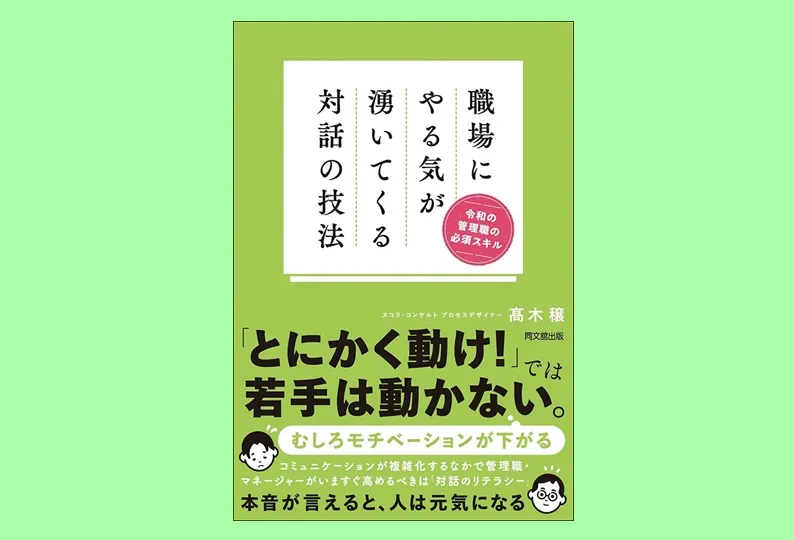スコラ・コンサルト
髙木 穣 プロセスデザイナー
【PROFILE】福岡県生まれ。トータル8回の転職を経験。組織開発コンサルタントのキャリアとしては、人事制度策定および研修開発のコンサルティング会社を経て、スコラ・コンサルトに入社。会社員時代の上司が急死した経験や、社員がメンタルで病んでいく現象を目の当たりにし、人が安心していきいき働けるための組織づくりの支援を目指す。人の気持ちを真正面から扱っているスコラ・コンサルトの「気楽にまじめな話をする場=オフサイトミーティング」に衝撃を受けて入社。以来、オフサイトミーティングを1,000回以上実施。メンタル不調者がゼロになった事例やV字回復した事例、親会社から独立した事例を経験する。組織変革への重要なファクターである、“場”づくりのプロフェッショナル。“場”の空気を読んだ振る舞いで“安心感”を醸成し、互いに自然体で話し合える“場”を創り出す。現在は福岡在住で、九州を中心に対話力向上研修や若手リーダー養成プログラムなどを行なっている。公開コースで対話力を磨く「マネジメント・ダイアログ・ジム」や対話コーディネーター研修も実施中。「ゆるさ」が持ち味。
「退職者が止まりません」「メンタル不調続出で残られた人も限界に近づいています」。最近、耳にする言葉です。簡単に会社を辞める存在の出現で、組織はその在り方を見直さざるを得なくなっています。
スコラ・コンサルトは40年近く前に会社を設立し、その頃から社会的にまだ認識されていない組織風土というものに着目してきました。当初、日本企業はあまり組織運営に問題意識を向けていませんでした。組織運営に関心がある会社でも、いかに社員を働かせ、いかに業績を上げるための仕組みへの対策でした。
その状況の中でもコミュニケーションとモチベーションが組織の大切な鍵だと感じた組織の方と一緒に改革に取り組んできました。そんな中、私たちが大切にしてきたのが「対話」です。
今では「対話が大事」と当たり前に聞きますが、ほんの10年前「対話」という言葉は企業の中では語られていなかったものです。上意下達の組織に対話は無用なもので、価値観がバラバラになってきて必要となった今でも「対話」をどのようにやったらいいかに組織は戸惑いを覚えています。
本書は私の組織変革の現場体験とわかりやすい知識をかけ合わせて、対話のマインドセットができるようにまとめてみました。
対話はやり方ではなく、在り方が大事だと思っています。その在り方にシフトするためには「どこに着眼するか」という観方や認識の仕方が重要になってきます。その認識を変えていくための図やフレームを多く紹介し、日ごろのコミュニケーションがより対話的になることを願ってコンパクトな本に仕上げました。
どうしても意思疎通が部下とうまくできない、組織をまとめることができない、そういった管理職の方がパラダイムシフトを起こし、職場に自然とやる気が湧いてくる対話を実現していただきたいと思っています。
これからAIもどんどん仕事の領域に入ってきます。だからこそ余計に人と人との心を合わせて進んでいく組織づくりのためにも活用していただけるとありがたいです。
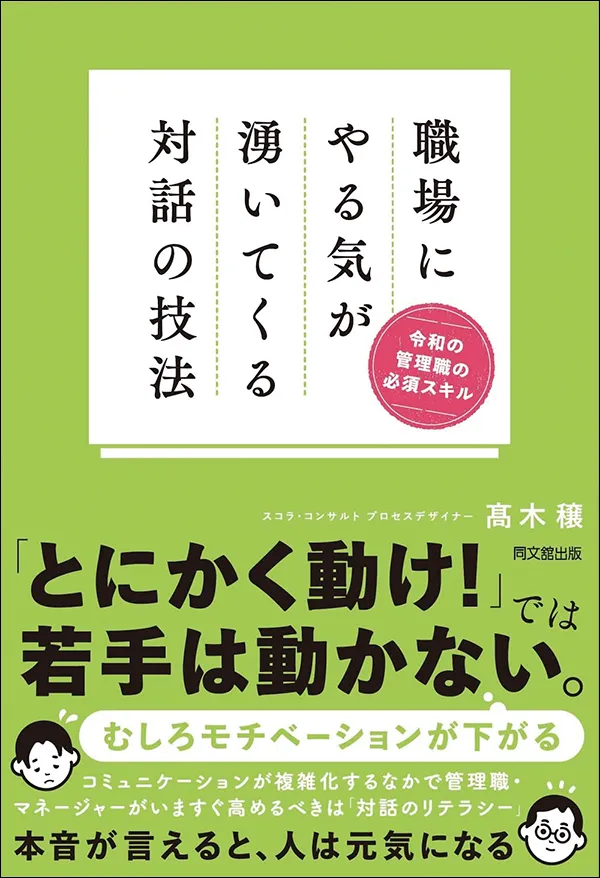
髙木穣 著
同文舘出版
1,600円+税