春闘の賃上げで実質賃金がプラスに転じるかどうかが注目されている。連合が7月3日に発表した今春闘の最終回答集計結果では、平均賃上げ率は5.25%と1991年以来の高い伸びを実現した。しかし、実質賃金の改善には毎月勤労統計調査における「定期昇給が反映されない」という構造的な課題があり、特に中小企業では物価上昇に追いつかない厳しい現実が浮き彫りになっている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)
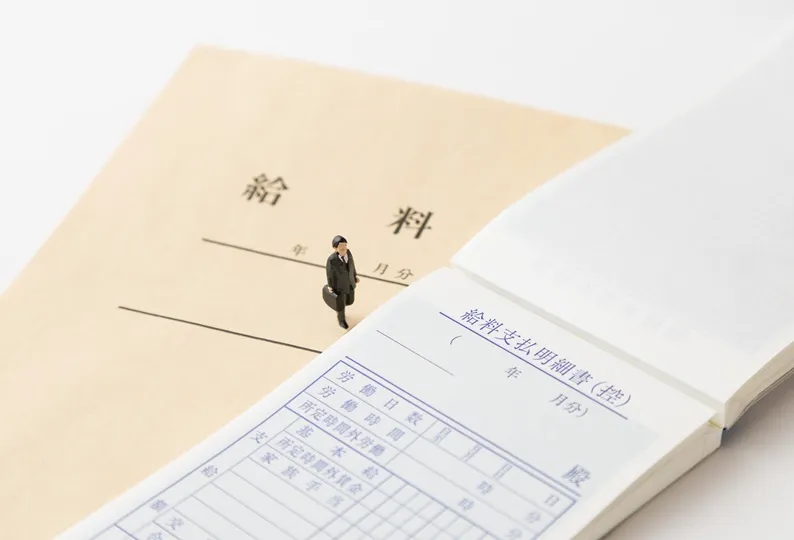
連合5.25%賃上げを達成も中小企業との格差が拡大
労働組合の中央組織の連合は7月3日、今年の春闘の最終回答集計結果を公表。5162組合の加重平均(規模計)の賃上げ額は1万6356円となり、賃上げ率は5.25%となった。昨年を0.15ポイント上回り、1991年の5.66%以来の賃上げ率となった。
5.25%には定期昇給分も含まれる。基本給を底上げするベースアップ分は1万1727円、率は3.70%と、昨年を0.14ポイント上回った。2年連続で定昇込み5%台の賃上げが実現したことについて連合は「定昇除く賃上げ分は過年度物価上昇率を上回った。新たなステージの定着に向け前進したと受け止める」と評価している(第95回中央委員会確認/2025年5月28日)。
ちなみに経団連の大手企業(従業員500人以上)の最終結果(2025年8月6日)によると、平均賃上げ額は1万9195円、賃上げ率5.39%で前年比0.19ポイント減となっているが、連合とほぼ同じ水準だ。
ただし全体の賃上げに影響するのは日本の労働者の7割を占める中小企業の動向だ。連合の300人未満の中小組合(3677組合)の賃上げ額は1万2361円となり、賃上げ率は昨年を0.20ポイント上回る4.65%となった。
内訳は100~299人の組合が4.76%(1万2909円)、99人以下が4.36%(1万922円)。1000人以上の賃上げ率が5.39%(1万7451円)であるのに対し、99人以下とは額にして6529円、率にして1.03ポイントの格差が開いている。
連合「2025春季生活闘争 第7回(最終)回答集計」の詳細はこちら
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2025.html
経団連「2025年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果[最終集計]」の詳細はこちら
https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/050.pdf
毎月勤労統計調査が映さない「定昇反映されない」統計の盲点
中小の定昇込みの賃上げ率4.65%は物価上昇率を上回るが、実は厚生労働省の「毎月勤労統計調査」には定昇が反映されないという特徴がある。
経団連の関係者は「毎月勤労統計調査の実質賃金の算出方法では定期昇給分は反映されない。賃金総額は前年との比較におけるマクロの金額であり、名目賃金は総額が前年にどれだけ増えたのかを調査しており、ベースアップしか反映されず、定昇込みの賃上げ率とは異なる」と語る。
定昇が反映されないとはどういうことなのか。経団連の「経営労働政策特別委員会報告2024年版」の「TOPICS実質賃金に関する考察」ではこう述べている。
<名目賃金は、調査対象事業所の「現金給与総額の合計」を「常用労働者数の合計」で除して労働者一人当たりの平均を算出している。この「賃金総額」による算出方法の場合、前年との比較において、ベースアップ分は数値に表れるのに対して、多くの企業で実施している定期昇給などの制度昇給分は数値に十分に表れない可能性に留意する必要がある。>
その上でこう述べる。
<例えば、労務構成の変化が毎年一定の企業を想定した場合、定期昇給など制度昇給を実施しても賃金総額は増加せず、名目賃金上昇率は「0%」となる。一方、同じ企業で2%のベースアップを実施した場合、賃金総額が2%増加するため、名目賃金上昇率は「2%」となる。>
確かに毎年一定程度昇給する定昇がある企業の場合、定年等で退職する人と新入社員の数がほぼ一定であれば賃金原資は変わらない。これを基準に前年と比べて増加した賃金原資を従業員一人当たりで割ると、ベア分しか反映されないことになる。
また、厚労省のホームページの毎月勤労統計調査における「利用上の注意」には「毎月勤労統計調査における名目賃金は、マクロの賃金データである。そのため、伸び率は『ベースアップ』の影響を受けやすく、各労働者の『定期昇給』による賃金増の影響は受けづらい」と説明している。
つまり、毎月勤労統計調査は「賃上げとはベアのことです」と言っているのに等しい。
中小企業のベア分では物価上昇に追いつかない現実
そうなると、連合の中小組合のベア分は3.49%、従業員99人以下は3.27%だった。過年度物価上昇率をかろうじて上回っているが、6月の消費者物価指数(総合)は3.3%と物価高騰が続いており、このまま続けば賃上げ分が相殺され、実質賃金がプラスに転じるのか微妙な状況にある。
実はこの賃上げ率も中小企業の実態を表しているとはいえない。一般的に労働組合のある企業はない企業よりも賃上げ率が高い傾向にある。日本・東京商工会議所は6月4日、「中小企業の賃金改定に関する調査」集計結果を公表しているが、調査対象企業のうち労働組合がある企業の割合は10.3%だった。
同調査によると、正社員の賃上げ額(月給)は加重平均で1万1074円、賃上げ率は4.03%。昨年比で0.41ポイントの増加となっているが、連合の中小組合の平均4.65%よりも低い。また、20人以下の小規模企業では、加重平均で9568円、3.54%となり、昨年比で0.20ポイントの増加となっているが、小規模企業ほど低い賃上げとなっている。しかもこの調査は定昇込みの賃上げ率であり、ベア分は明らかではない。
賃上げ額・率を都市部(東京23区・政令指定都市)と地方(東京23区・政令指定都市)で見た場合、都市部の正社員の賃上げ額は加重平均で1万2857円、賃上げ率は4.37%、地方は1万627円、賃上げ率3.94%。地方の小規模企業の場合は、9269円、賃上げ率3.55%と、さらに低くなっている。
「中小企業の賃金改定に関する調査」の詳細はこちら
https://www.jcci.or.jp/news/research/2025/0604153019.html
一般的に定昇がある企業は2%程度といわれる。そうであれば5%強の賃上げ率でなければ物価上昇率を上回り、実質賃金がプラスになることはない。仮に中小企業の定昇が1%だとしても、4%以下の賃上げ率では実質賃金はマイナスになる。
大企業の社員は物価を上回る賃金を得られる一方、中小企業の従業員は物価を下回る賃金しか得られず、苦しい生活を強いられることになる。








