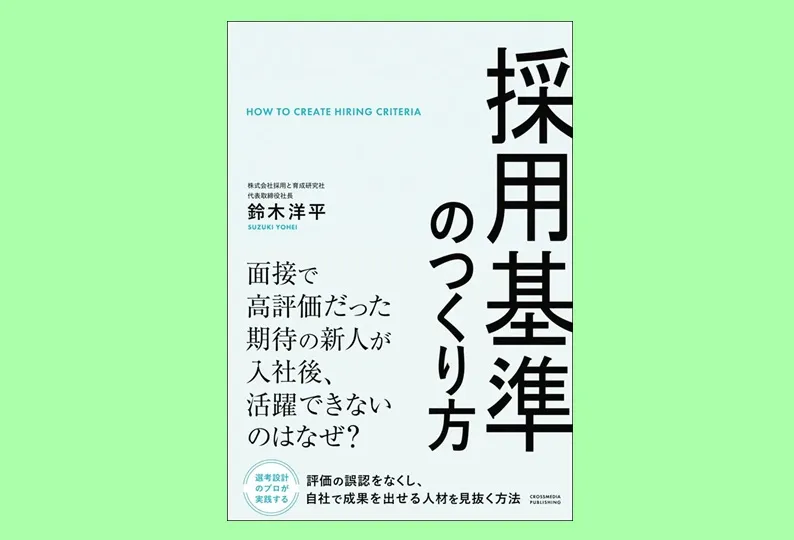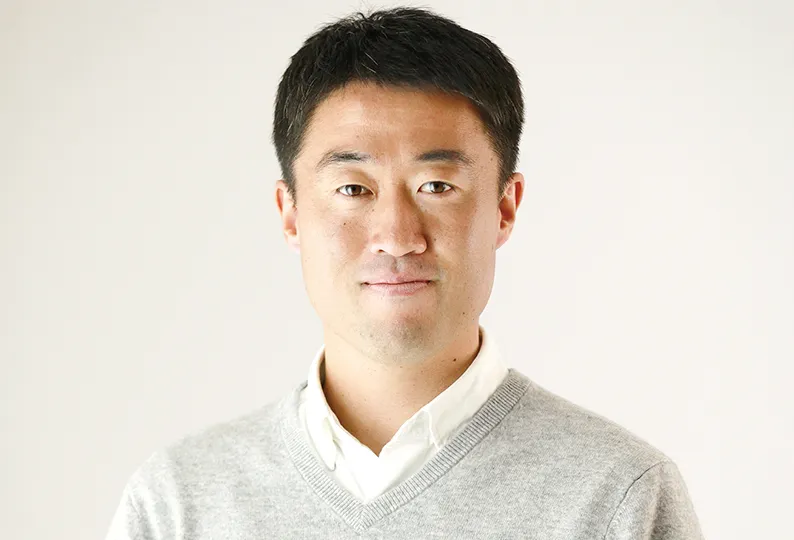
採用と育成研究社
鈴木 洋平 代表取締役社長
【PROFILE】2002年日本アイ・ビー・エム株式会社入社。SEとして入社後人事に転身。コンピテンシーを活用した昇進評価制度の設計、展開、運用を担当。2008年4月株式会社採用と育成研究社を設立、同取締役就任。2025年3月同取締役社長就任。日産自動車をはじめとした、大手企業の社員向けアセスメントプログラムの開発を行い、講師も務める。その他、採用活動コンサルティング、大学生向けキャリア形成支援プログラムなど多くのプロジェクトを手掛けている。
・米国CCE,Inc. 認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー
・認定AI(Appreciative Inquiry)ファシリテーター
・認定ワールドカフェ ファシリテーター
本書のテーマは「採用選考における評価の質の向上」です。採用では「応募者を集める」「応募者に選んでもらう」といった領域である採用マーケティングが注目されがちです。
もちろん、自社にとってよい人材を獲得するためには採用マーケティングも重要です。ところが、せっかく応募してくれた人材の評価を誤ってしまっては応募者の合否の入れ替わりが発生してしまい、採用の目的を達成できません。
そこで本書では、普段注目されることの少ない採用選考にフォーカスし、評価の精度を向上させるための方策について解説しています。
選考で評価を誤りやすい要因のひとつとして、面接に対する盲目的な信頼が挙げられます。面接には、評価の誤認につながる3つの落とし穴があります。この落とし穴は、よく指摘されている面接官の認知バイアスとは別の、面接そのものが抱えている構造的な要因によるものです。
面接は万能ではありません。この前提に立ち、本書では評価精度の向上について大きく2つのポイントに分けて改善の方法を紐解いています。
1点目は、応募者の何の能力を評価するかを決定するための採用基準の定義についてです。評価する対象の能力を誤ると、選考そのものが意味を成しません。採用基準と混同しがちな評価基準の説明も含め、4つのステップでの採用基準の定義を紹介しています。
2点目は、採用基準の能力をできる限り正しく評価するための選考方法についてです。100%正確な能力評価はできませんが、より精度を高めることで合否の入れ替わりを最低限におさえることができます。
評価精度を高めるための「評価手法の選択」「選択した手法における評価の方法の設計」「評価者への教育と実践」の3点について順を追って解説しています。特に、評価手法については行動観察手法が面接より優れている点を示し、その設計方法を具体的に紹介しました。
他にも、応募者に自社を選んでもらうための志望動機の共同構築の方法など、現場で使える知見を盛り込んでいます。本書が採用選考の改善に少しでも役立てば幸いです。
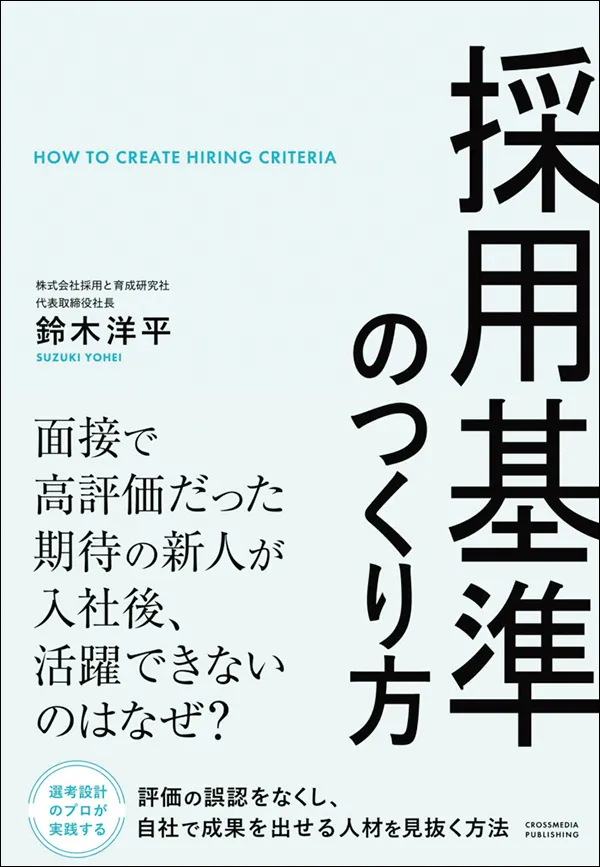
鈴木洋平 著
クロスメディア・パブリッシング
1,750円+税