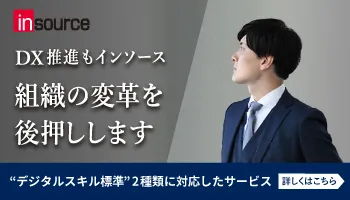大阪市の印刷会社の労働者が相次いで胆管がんを発症し、死亡者を出した問題が全国的に波紋を呼んでいる。厚労省の全国の印刷会社に対する立入検査などで安全衛生管理の不備が明らかになっており、発症の原因究明とともに安全衛生管理に対する企業責任が改めて問われそうだ。(文・溝上憲文編集委員)

胆管がん発症問題では、原因物質とされる有機塩素系溶剤を使用する印刷事業所は多く、胆管がんに関連する労災請求は45人(10月12日現在)に上っている。
発端となった大阪市の印刷会社は従業員約70人のオフセット校正印刷を専門とする会社だ。今年9月までに13人(元従業員を含む)が胆管がんを発症し、7人が死亡している。
元従業員の相談を受けてこの問題を最初に公にしたのは、産業医科大学の熊谷信二准教授である。熊谷准教授の症例報告は日本産業衛生学会の抄録集に掲載されているが、それによると校正印刷部門の5人の元男性従業員(勤務歴8~11年)が肝内胆管がん、あるいは肝外胆管がんを発症し、4人が死亡。
発症年齢は25~45歳と若く、入社から発症までの期間は7~19年。原因物質としては校正印刷の作業中に使用していた洗浄剤に含まれる有機塩素系溶剤の1.2-ジクロロプロパン、ジクロロメタンなどの化学物質が疑わしいとしていた。
厚労省は5月の後半以降、労働安全衛生総合研究所の専門家と一緒に印刷会社に何度も立入調査を実施。さらに会社の実際の作業現場で環境測定の模擬実験も行った(測定結果は8月31日に公表)。
一方、6月には大阪の会社と同様の洗浄作業をしている561社の印刷会社の立入調査を実施している。7月10日には立入調査の結果と複数の胆管がんが発生している労災請求があった大阪と宮城の印刷会社についての中間報告書をまとめている。
それによると、校正印刷の作業場は地下1階にあり、作業は昼夜2交代で行われていた。オフセット校正印刷は色見本を作成する作業であり、1色だけ刷るのを単色機、赤、青、黒、黄の4色を同時に刷るのを4色機と呼ぶが、ここでは単色機5台が設置されていた。
工程はまず校正機に版をセットし、ローラーに赤インキをヘラで塗り、ローラーを回転させて赤インキを巻く。続いてブランケットと呼ぶゴム製のロールに転写し、最後に紙に印刷する。単色機なので同じ機械で青、黒、黄のインクで同様の作業を繰り返す。
問題は洗浄回数だ。1色の印刷が終了するとインキロールとブランケットをその都度洗浄する必要があり、1種類の印刷で計5回洗浄する。色見本を作成するために一気に何千枚も刷ることはなく、1種類につき10枚程度印刷したら別の色見本の印刷に入る。当然、洗浄回数は多くなる。熊谷准教授の調査では、1日300~800回の洗浄が行われていたという。
厚労省が問題視したのは、洗浄回数の多さに加えて、有機塩素系溶剤の洗浄剤を使ってブランケットを手で洗っていたことだ。
厚労省の担当者は「印刷会社の中には自動洗浄もあるが、大半の印刷会社は手で洗っている。目の前に突きだした印刷機のローラーを手で拭いているということは、口元の近くに有機溶剤の発散源があるということであり、必然的に暴露の量が多くなる」と指摘している。
洗浄時は手袋を着用しているが、呼吸保護具はしていない。ここまでは印刷会社共通の作業実態である。大阪の印刷会社はこれに加えて換気が著しく悪かったことだ。作業所は地下であるために窓はないが、全体循環系と床面の排気系の2つの換気設備はあった。
ところが床下の排気は作業場面から1メートルも離れていた。掃除機で1メートル先のものを吸い込むのと同じで発散を抑制するものではなく、全体の換気設備もオフィスの空調と同じで内部の空気を還流させるもので有害物を排気するものではなかった。問題は有機溶剤で使用されていた化学物質の正体である。
厚労省は1991年から2006年までに使用されていたと考えられる洗浄剤が会社に納品書が保存されていなかったため、大阪労働局が納入業者から入手した伝票や元従業員の聞き取り調査の結果、長期間にわたって使用されていた洗浄剤の成分は、ジクロロメタン(以下DCM)、1.2-ジクロロプロパン(以下DCP)、1.1.1-トリクロロエタンであった。
労働安全衛生総合研究所との共同による模擬実験では、裏付けがとれたDCPと使用された可能性が高いDCMの溶剤を使って拡散状況を調べた。その結果、両成分を大量に暴露していたことが分かっている。
しかし、厚労省の7月10日の報告書および安衛研の報告書はここまでに留まる。肝心のDCPおよびDCMが胆管がん発生の原因物質であるかどうかについては現在調査中だ。
現在、因果関係の解明に向けた「疫学的調査」を大阪市立大学のグループに依頼している。調査はDCPなどの化学物質を対象に動物試験を行い、生体内での化学物質代謝メカニズムの解明を進める予定だ。
仮にDCPやDCMなどの有機塩素系溶剤が胆管がんと因果関係があるにしても、大阪や宮城の印刷会社の特殊な環境によるものなのか。大半の印刷会社は手を使って洗浄していると前述したが、厚労省は今年6月中旬から末にかけて洗浄作業を行っている561の事業場の立入調査を実施している。
その結果、規制対象の有機溶剤を使用している事業場は494あり、法令違反など何らかの問題が認められた事業場は383(77.5%)もあった。中でも作業環境測定の未実施181件、特殊健康診断の未実施、呼吸用保護具の未使用が121件もあった。
違反率70%以上という事態を重くみた厚労省は全国の約1万8000社に対して郵送による通信調査を7月末に実施した。今年8月末までの回答状況は、有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象物資を使用していると回答した事業場は7009、未回答は3864であった。
厚労省は現在、対象物質を使用している事業場および未回答事業場の事業者を呼んで有機則の順守徹底を図るための集団説明会を実施している。
一連の調査では胆管がんの発症者数も聞いている。6月の立入調査では大阪・宮城の会社を除く3事業場3人。通信調査では22事業場22人が発症していた(労災請求の事案は除く)。前述したように10月12日時点の労災請求は9月の34件から新たに11人増えて45人(死亡29人)となった。この申請事案についても厚労省の検討会で審議されることになる。
適正な安全衛生管理を怠っている事業所が多いことを考えると、申請件数は今後さらに増える可能性もある。