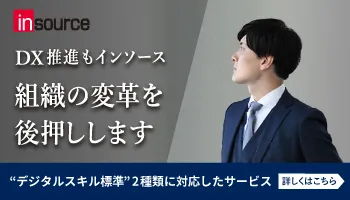政府の働き方改革で注目されていた「時間外労働の上限規制」の議論が進み、2年後には法改正が行われる予定だ。生産性向上や社員の健康確保に向けて、形式的な残業規制にとどまらない人事の取り組みが必要になっている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)
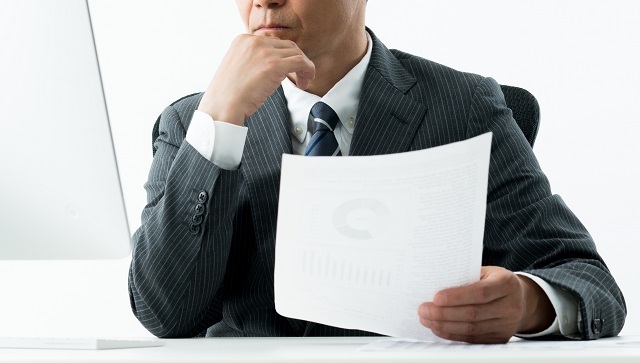
残業の上限は「月100時間未満」で決着
安倍政権の働き方改革実現会議が「働き方改革実行計画」を発表した。 最大の目玉は「時間外労働の上限規制」と「同一労働同一賃金原則」の法制化であることは間違いない。
これまで法的に青天井だった残業時間に年間720時間(月平均60時間)を上限とする労働基準法の改正議論がすでに厚労省の審議会で始まっている。一方、同一労働同一賃金については昨年末に「ガイドライン案」が出されたが、ガイドラインとして施行されるのは法改正の施行時(工程表では2019年4月予定)である。
その法改正の議論は今後、労働政策審議会の労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法を所管する各分科会の下に「同一労働同一賃金部会」を新たに設置して行われる。ただし、裁判の立証責任を使用者側に持たせるのかどうかを含めて、法律案を巡っては労使の利害が絡むいくつかの論点が存在し、その行方は混沌としている。
それに対して上限規制は働き方改革実現会議で大枠が決定され、最後は1カ月の残業時間の上限を100時間までなのか、それ以下にするのか揉めていた労使の議論が続いていた。
その結果、安倍晋三首相が日本経済団体連合会(経団連)の榊原定征会長、日本労働組合総連合会(連合)の神津里季生会長と首相官邸で会談を行い、残業の上限を「月100時間未満」にするように要請したことで決着した。
その内容は現行の労使で結ぶ協定(36協定)の限度基準告示である月45時間、かつ年間360時間を法律に明記し、これを超えた場合は罰則を科す。さらに特例として、次の労使合意内容も労基法に明記することになった。
1.年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする
2.休日労働を含んで、2カ月ないし6カ月平均は80時間以内とする
3.休日労働を含んで、単月は100時間未満とする
4.月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないものとする
この上限を超えたら罰則が付くことになる。つまりに特例として労使協定を前提に年間の時間外労働時間の上限を720時間とし、その範囲内で月45時間を超えるのは6カ月までとし、繁忙期は「2~6カ月の平均で80時間を超えない」かつ「きわめて忙しい1カ月の上限は100時間未満」とする歯止めをかけることになった。
つまり残業時間が年間720時間を超えた場合に限らず、1カ月100時間超、2カ月や3カ月平均でも80時間を社員が1人でも超えた場合、確実に摘発・送検される絶対的な上限規制になる。 だが、この規定が法制化されても企業が運用するとなると混乱するかもしれない。
特例の年間720時間の様々な条件に加えて「時間外労働」と「休日を含んで…」の2つに区分されている。なぜか。労基法は法定労働時間を超える時間外労働と法定休日の休日労働を別の規定で規制している。時間外労働という場合は休日労働を含まない。
一方、いわゆる過労死認定基準が時間外・休日労働を含めたものとしているため2カ月80時間、単月100時間未満は「休日労働を含む」としたものだ。
法律の根拠はともかく、企業の労務担当者には分かりにくい。時間外労働時間と休日労働時間を分けて会社の上限時間を設定しなくてはならなくなる。
上限規制施行で、一人でも違反すれば摘発・送検
いずれにしても今回の上限規制の趣旨は労働者の過労死防止など健康確保にある。1カ月の上限を100時間未満にしたところで2~6カ月の平均で80時間の上限が容認されると、過労死基準に抵触し、過労死の発生を防止することはできない。
月80時間の残業だと週20時間。週5日勤務で1日の残業時間は4時間。9時始業・18時終業(実労働時間8時間)の会社では毎日10時まで残業、帰宅するのが11時過ぎという生活が2カ月連続するだけで、心身がへとへとになる可能性もある。
では人事担当者はどのように受け止めているのだろうか。食品業の人事部長はこう指摘する。
「年間の残業720時間は結構長いという気がする。6カ月の月平均80時間だと労災認定基準に抵触してしまう。難しいのは健康には個人差があり、月100時間残業しても長時間労働だと思わない人もいれば、月40時間でも身体が持たないという人もいる。悪質な経営者は限度時間を逆手にとって法定内だから子育て中の社員にも限度時間いっぱいの残業をやらせるかもしれない」
一方、住宅設備関連メーカーの人事担当者は第一歩として評価する。
「法律的には事実上青天井であり、一定の歯止めをかける効果はあるだろう。ただ、我々メーカーにとっては季節の繁忙期があり、一律に月60時間になると厳しい。月最大100時間、2カ月の月平均80時間が認められれば何とかクリアできそうだ。以前は80時間、100時間超えの社員は珍しくなかった。現在では社員の月平均残業時間を45時間程度にまで下げたが、繁忙期があるうえに、取引先との関係でどうしても突発的な仕事も発生する。今回の規制は妥当な線ではないかと思う」
逆に上限規制に危機感を募らせるのはゲーム関連会社の人事課長だ。
「うちも様々な残業削減策を講じているが、ゲームクリエーターは帰れと言っても帰らない社員も多い。それだけ仕事が楽しくてしょうがない。自宅でも寝ないで平気で仕事に没頭する社員もいるし、人事が注意すると『好きで仕事をやっているんだからほっといてくれ、倒れそうになったら自分で休むから大丈夫だ』 と反発してくる。法律が施行されたら立件される恐れがあり、なんとかしないといけないが、できれば職種によって適用除外を検討してほしい」
企業によって評価は異なるが、果たして上限規制の法的効果はどれぐらいの人たちに及ぶのだろうか。
厚労省の委託調査(「過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業報告書」2016年3月、対象労働者1万9583人)によると、正社員の平均的な1週間当たりの残業時間は「10時間未満」が58.1%、「10 時間以上20時間未満」が22.7%、「20時間以上」が10.0%存在する。
週20時間以上の人は上限に抵触する可能性があるが、大半の社員は月平均60時間以内に収まっていると推測できる。 だが、上限規制が施行されると、社員の一人でも違反すると摘発・送検される。
公共事業の発注中止に追い込まれるなど社会的信用を失うだけに、絶対に避けるために今以上に残業規制を厳しくしてくるだろう。
だが、そうなると別の影響も懸念される。
建設関連企業の人事担当者は「上限規制で残業制限を厳しくすれば、社員は陰に隠れて早出してやるとか、家に持ち帰ってやるなどサービス残業をやってしまう社員も出てくるかもしれない」と不安がる。
実効性の確保に向けた業務プロセスの見直しへ
東京商工リサーチが企業に対して実施した「『長時間労働』に関するアンケート調査」(2017年3月10 日)では「残業時間の上限が決まり、現在より労働時間が短縮する場合に予想される影響とは何か」を聞いている(複数回答)。
大企業では、トップの「仕事の積み残しが発生する(31%)」に続いて「持ち帰り残業が行われる懸念(16.7%)」が挙がっている。そのほか「従業員の賃 金低下(11.1%)」にも影響すると回答している。
これは残業時間が減れば、仕事の積み増しが発生する。その分を持ち帰り残業というサービス残業でカバーするが、残業代が出ないので社員の給与が減る――というふうになると解釈できる。
もし予想通りになれば“隠れ残業”が横行し、給与が減らされた上に心身に負荷がかかるという健康確保とは真逆の結果になりかねない。
前出の厚労省の委託調査の企業アンケートでは、労働時間の把握方法が「タイムカード、ICカードなど客観的記録で確認している」企業は47.4%。上司などが「直接始業時刻や終業時刻を確認している」が25.4%、「労働者が自己申告している」企業が21.5%となっている。
上司が意図的に残業時間を操作する、社員本人が少なく申請する余地が残されている。ちなみに同調査では「持ち帰り仕事がある」と答えた人は34.5%。その頻度はほぼ毎日という人を含めて週2~3回以上の人が合計29.5%に上っている。
上限規制を実施しても実労働時間が変わらないという事態は避けたい。
各企業が実施している「ノー残業デー」「定時退社」のみを実施している形式的な残業規制の構図と同じだ。たとえ外から規制しても“隠れ残業”が横行することになる。
政府が実施する上限規制はあくまでも企業が長時間労働を是正するための誘導策にすぎない。実効性を持たせるかどうかは、企業自身が業務量を含めた業務プロセスの見直しなど地道な取り組みがより重要になるだろう。