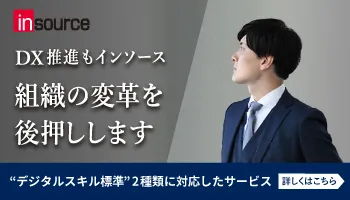深夜労働、日曜・祝日労働などの労働時間規制の適用を外すホワイトカラーエグゼンプション(以下、エグゼンプション)制度の全容が明らかにされた。2月13日、厚労省の労働政策審議会の報告書が厚生労働大臣に建議。今後、法案化され、閣議決定を経て今通常国会に「労働基準法改正案」として国会に提出される予定だ。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

報告の中には、中小企業の月60時間超の時間外割増率50%の義務づけ(2019年4月から)や年5日以上の年次有給休暇取得を企業に義務づける内容も盛り込まれている。だが、最大のポイントはエグゼンプションの導入と企画業務型裁量労働制の適用者の拡大だ。
エグゼンプションは新たに「高度プロフェッショナル制度」と命名された。言うまでもなく適用者の「残業代」の支払い義務がなくなる。具体的なポイントは次の通り。
1.対象業務は、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等
2.平均給与額の3倍を相当程度上回る年収。具体的な年収基準は1075万円以上
3.希望しない人には適用しない
4.健康確保措置として企業労使は次の3つのいずれかを選択する
①終業から始業まで一定の休息時間を与える(インターバル規制)。深夜業は1カ月について一定の回数以内。
②1カ月または3カ月の労働時間の上限を設定する。
③4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日を与える。
一見すると、対象業務を限定した上に年収が1075万円以上であり、ほとんどの人は関係ないと思うかもしれない。だが、対象業務の拡大や年収が引き下げられる余地も残されている。実は1の業務と2の具体的年収は法律に明記されることはなく、「省令」で規定する予定だ。
法律と違って省令は国会審議を経ることなく、政府の意向で容易に変更できる。年収についても省令改正で引き下げられる可能性があるとの労働側委員の批判を受けて「平均給与額の3倍を相当程度上回る」という文言が法律に書き込まれた。平均給与額とは厚労省の「毎月勤労統計調査」の「決まって支給する給与」の12カ月分。2013年の月平均給与額は約26万円。その3倍は936万円だ。
新制度では上記で示したように健康確保措置を設けている。①はEUのインターバル規制を想定しており、②は労働時間の絶対的な量的上限規制を設けるものだ。「一定の時間」や量的上限規制の労働時間は、法案成立後、省令で規定する予定だ。健康確保に有効な仕組みであるが、選択肢の一つにすぎない。
しかし、おそらく多くの企業が選択するのは③の4週間4日、年間104日以上の休日の付与――を選択する可能性が高い。なぜなら現在の年間休日総数の1企業平均は105.8日、労働者1人平均は112.9日(2013年、厚労省調査)。企業にとって最もクリアしやすい基準だ。
もう一つの「企画業務型裁量労働制」の拡大は以前から経済界が求めていたものだ。その内容はほぼ満額回答ともいえるものだ。まず、手続きについてはこれまで事業所単位で最寄りの労働基準監督署に届け出る必要があったが、本社一括届出を認めている。
さらに半年ごとに求められる定期報告は、6カ月後に一度行えばよいことになった。そして対象業務は次の2つが追加された。
①法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)
②事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務
①はいわゆる提案型営業(ソリューション営業)、②は営業以外の何らかのプロジェクトに従事している「プロジェクトリーダー」に当たる人と思われる。実現すれば導入企業が大幅に増えると予想される。
だが、一定の歯止めはあるもののエグゼンプションの導入と裁量労働制の拡大で長時間労働が増える懸念がある。本来、エグゼンプションに限らず、裁量労働制の適用者は、自分の裁量で仕事をこなし「出勤・退社時間の自由」が原則だ。政府も仕事と子育てとの両立が可能になると推奨している。
しかし、現実はそうなっていない。導入企業の実態は裁量労働制を適用されていない社員より労働時間が長い上に、49.0%の人が「一律の出退勤時刻がある」と答え、40%超の人が遅刻した場合は「上司に口頭で注意される」と答えている(労働政策研究・研修機構2014年6月調査)。
現行の企画業務型裁量労働制の適用労働者は0.3%程度にすぎない。営業職が認められたことで導入企業が増えれば、時間管理のあり方を含めて現場で混乱する可能性もある。