
NTTグループ、初任給を14%引き上げ
今年の春闘で初任給を大幅に引き上げる企業が相次いでいる。
NTTグループは昨年11月、主要会社の大卒初任給を2023年4月から14%引き上げると発表した。現行の21万9000円から25万円。採用時点で専門性が高いと判断した人材は27万2000円以上にする。
NTTの島田明社長は記者会見で「ICT(情報通信技術)の分野は非常に競争が激しい。デジタル人材をしっかり確保しなければビジネスにならず、魅力ある会社にする」と語っている。
【賃金に関するおすすめ記事】
大手銀行3行でも相次ぐ初任給引き上げ、定着にも強い危機感
NTTは人材の獲得だけではなく、定着についても強い危機感を感じているようだ。
人材の獲得と流出への危機意識は同社だけではない。これまで初任給が低かったメガバンクも相次いで初任給を引き上げた。
三井住友銀行は今年4月から初任給を25万5000円、みずほフィナンシャルグループは24年4月入社の社員から26万円に引き上げる方針だ。三菱UFJ銀行も5万円引き上げる方針だ。
3行は長らく20万5000円で横並びだった。引上げの背景には、内定を蹴って商社や外資系コンサルティング会社を選ぶ学生が多いからという説もある。
ファーストリテイリングも国内従業員の年収を数%から最大約40%引き上げたことで注目を浴びた。しかも初任給も25万5000円から30万円に引き上げた。初任給は年収で約18%アップという破格の引き上げだ。
同社の初任給は給与水準としては国内企業で高いほうだが、それでも海外大手企業に比べると見劣りする。
新卒を外資系企業に奪われてきた現状
相次ぐ大手企業の賃上げの背景にあるのは人材獲得競争の敗退がある。
日本の賃金が上がらない理由は歴史を振り返ると、バブル崩壊以降、物やサービスの付加価値創造よりもコスト削減、つまり賃金を抑制する事業戦略を優先させてきたことにある。
その結果、賃金抑制の歪みで企業の人材獲得競争力が失われている。
デジタル化などイノベーションによる付加価値創造には優秀人材の獲得が不可欠だが、今では新卒を含めて外資系企業に奪われているのが実態だ。
大卒初任給は諸外国に比べても低い。ウイリス・タワーズワトソンが諸外国の大卒入社1年目の2019年の基本給(年額)を調査している(『日本経済新聞』2020年4月21日)。
最も高いのはスイスの800万円超、続いてアメリカの632万円、ドイツの534万円。ノルウェーが400万円超、フランス、スウェーデンが400万円となっている。
日本は韓国、シンガポールよりも低い262万円。2019年の為替レートは110円前後で今ほどの円安ではない。世界的に低い初任給が結果的に人材獲得競争力も失わせている。
中堅・中小企業は、初任給を引き上げたくても引き上げられない
最近の初任給引き上げの動きについて人材紹介業大手ジェイエイシーリクルートメントの黒澤敏浩プリンシパルアナリストは以下のように語る。
「IT系企業を中心に若手の給与を引き上げる企業が増えている。給与を低いままにしておくと、競合他社の草刈場になってしまう恐れもあり、賃金全体の底上げをせざるを得ない状況になっている」
しかし、初任給を引き上げたくても上げられる企業ばかりではない。
中堅・中小企業の事情に詳しい組織人事コンサルタントは「物価が高騰し、賃金の上昇機運が高まっていることは理解しているが、今までと違ってどのくらい上がっていくのかわからず、恐怖に近い感じを抱いている中堅企業の経営者が多い」と語る。
中小企業の賃上げ交渉が本格化しているが、現時点では初任給を引き上げるのか様子見の企業が多いという。コンサルタントは「決定まで至っておらず、地域や同業他社の動向を探り、少なくとも平均額で負けない程度の金額を探っている状況だ。仮に引き上げるにしても数千円レベルになるのではないか」と指摘する。
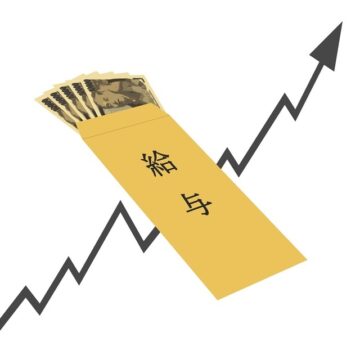
初任給引き上げに伴う最大の問題
引き上げるにしても最大の問題は初任給だけではすまないということだ。
なぜなら初任給を引き上げると、その上の在籍している社員の賃金も同時に引き上げないと、下手をすれば新入社員と同じ給与になってしまう。そうなると在籍社員の不満も噴出する。結果的に人材の流出を引き起こす危険性もある。
初任給を引き上げると、とくに年功型賃金制度を導入している企業ほど固定費は一層膨らむことになる。
もちろん会社の業績が毎年伸びていくのであれば可能だが「5年後、10年後も利益が上がり続けていく見通しを持っている経営者は皆無だろう」(コンサルタント)というのが実態だ。
ジョブ型賃金への移行が賃金引き上げの契機となるか
ではどうするのか。
コンサルタントは「活躍している人とそうでない人を分けるなど評価制度も含めて賃金制度をゼロから見直すしかない。経営者には制度の変革の覚悟が求められているが、すでに着手している企業もある」と語る。
つまり従来の年功賃金から成果型、あるいは流行のジョブ型賃金への移行である。
実は大企業もジョブ型賃金への移行が進んでいる。
例えばジョブ型賃金の導入にあたっては、社員の現在の職務内容を分析し、市場価値に連動した職務ごとの賃金をレベル化した職務等級に当てはめる。
その結果、給与が上がる社員もいる反面、下がる社員も発生する。
昨年10月に月給で平均4%引き上げたロート製薬も年齢給を廃止し、職務給重視の制度を導入した。
同社の杉本雅史社長は「具体的には年齢給を廃し、職務給に重点を置いた。これまで年齢給と職務給の比率は3.5対6.5ぐらいだったが、どんな仕事をしているかで給与が決まるようにした」と述べている(『日本経済新聞』12月19日付朝刊)。
年齢給を廃止し、新たな職務等級に当てはめると当然、給与が下がる社員も発生する。
杉本社長は「一部の社員には給与水準が下がるケースが生じる。そこで移行期における減少分は補填する形にして、不利益変更にならないように意識した。ただ2年間の時限措置とし、本人に一つ上の職務レベルで仕事を担う覚悟を持って昇格に挑戦してもらうことを期待している」と述べている。
賃金を引き上げても離職率が減らないワケ
今回の初任給を含む賃上げを契機に年功型賃金から成果型あるいはジョブ型賃金導入に拍車がかかる可能性もある。
しかし、そうやって初任給を引き上げても、新卒の離職防止に歯止めがかかるとは限らない。
大手食品会社の人事担当役員は「初任給を30万円に引き上げる企業もあるが、おそらく離職率はそれだけでは変わらないだろう。入社しても、自分がやりたいことができないとわかった瞬間に、会社がどんなに引き留めても辞めていく傾向は変わらない」と語る。
ではどうすればよいのか。
人事担当役員は「今の若い人たちは即戦力として扱ってほしいという志向が強い。昔のように入社後2~3年は雑巾がけだと言ったらすぐに辞めてしまう。入社1年目は学ぶ期間であっても2年目以降は、それなりに責任ある仕事を任せるようにする。失敗することを織り込みながらスモールサクセスを積み上げていくことで自信につながる。そうした組みや機会を多く用意することが仕事だ」と語る。
初任給の引き上げは体力のある企業が有利であることは間違いない。
しかし、それだけに引きずられることなく、入社後の働き方や仕事の任せ方など工夫していく余地は十分にあるのではないか。







