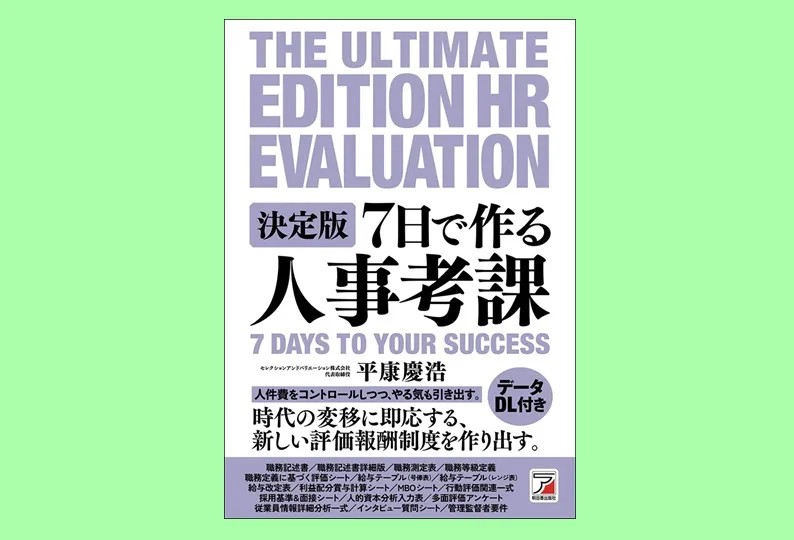セレクションアンドバリエーション
平康 慶浩 代表取締役
【PROFILE】1969年大阪生まれ。アクセンチュア、アーサーアンダーセン、日本総合研究所を経て現職。大阪市立大学経済学部卒、早稲田大学大学院ファイナンス研究科MBA取得。グロービス経営大学院客員准教授。特定非営利活動法人人事コンサルタント協会理事。大阪市特別参与として区長・局長・部長公募面接、校長公募面接を務める(2011年~2016年)。ファイズホールディングス(東証スタンダード上場) 独立社外取締役、報酬委員会議長(2017~2023年)。
今年あなたの会社に入社した新人が、定年まで在籍している可能性はどれくらいでしょうか。65歳定年で43年後、70歳までだと48年後です。そんな先のことは、もはや誰にもわかりません。だからこそ、これからの10年に生かせる人事制度が必要ではないでしょうか。
前著「7日で作る新人事考課」上梓から10年が過ぎた今、あらためて、どのような人事の仕組みが求められるかをまとめてみようと思いました。
「7日で~」というタイトルは、正直なところ、出版社による宣伝の意図があります。けれどもタイトルが嘘にならないよう、本当に7日で人事制度を新しく作るためのステップを示しました。それが本書の前半である「ファストトラック編」です。立ち上げたばかりのベンチャーや社内起業した数十人程度の組織に向けて、「昇給のあるジョブ型」の設計方法を具体的なフォーマットとともに示しました。
それに加え「詳細設計編」と題し、大企業などの既に確固たる人事制度がある会社向けに、環境変化に合わせた制度改定の方法を記しています。
そこで重要なポイントは「人事戦略」としてのグランドデザインです。ステークホルダーたちが改革の方向性に合意し、一枚岩で新しいマネジメントスタイルを構築していくための手順を記しました。「等級」「報酬」「評価」の各仕組みについては、単一の方法を示すのではなく、ビジネスモデルや組織文化に合わせた複数の選択肢を示しました。
そして何よりも重要な点として、制度をしっかり機能させる「採用から代謝までの運用フロー設計」「新制度への移行措置」「企業文化としての定着」についての章をそれぞれ設けています。これからの10年に生かせる人事には次の三つの特徴があるからです。
第一に、労働市場を前提とした「選ばれ続ける仕組み」。第二に、働く側の「多様性を前提とした仕組み」。第三に、「利益を生むことを強く求める仕組み」です。
無料ダウンロードが可能な20本のサンプルフォーマットも用意しています。ぜひこれからの人事改革にお役立てください。
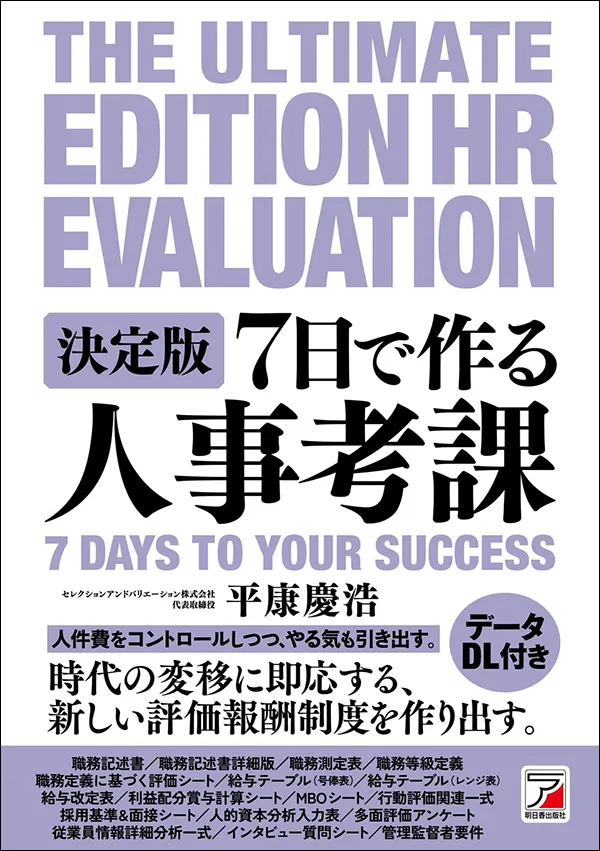
平康慶浩 著
明日香出版社
2,500円+税