日本学生支援機構では2021年4月、各企業等で実施している奨学金返還支援について、一定の条件下で、企業からの送金を直接受け付ける「奨学金返還支援(代理返還)制度」を創設した。各企業がこれまで行っていた、支援額を給与に上乗せする形での返還支援とは異なる、本制度の概要及び活用のポイントと留意点について、丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)
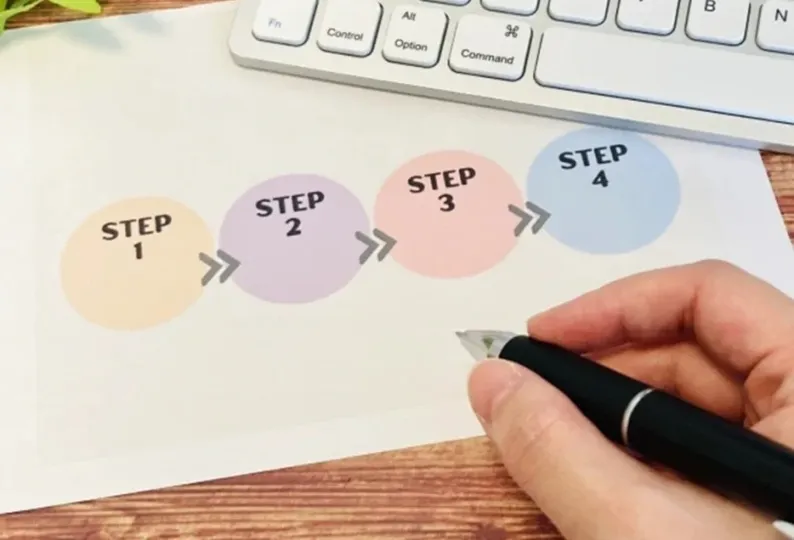
学生の3人に1人が奨学金を利用する昨今、企業による返還支援は若手人材確保・定着のカギに
日本学生支援機構の調査によると、2023年度に同機構の奨学金を利用した大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)の学生の数は117万人とのことで、これは363万人いる学生全体のおよそ3人に1人に相当します。
多くの学生が奨学金を活用して学校を卒業し、その後奨学金返還を抱えながら社会人生活を営む現実に鑑みれば、若手人材の就職先選択に際し、奨学金返還支援制度の有無が与える影響は決して小さくないことが予想されます。
とりわけ中小企業においては、大企業のような賃金引き上げへの対応が難しいとしても、福利厚生としての奨学金返還支援制度の創設によって、若手人材への訴求力向上を図ることができそうです。さらに、奨学金返還支援はある程度長期に渡ることが想定されますから、人材定着の観点からも良い効果が期待されます。
参考:独立行政法人日本学生支援機構「奨学金事業に関するデータ集 令和7年1月[令和7年6月一部改訂]」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin_data/index.html

従来型の支援とは何が違う? 新設「奨学金返還支援(代理返還)制度」を知る
企業が従業員の奨学金返還を支援する仕組みはこれまでにも各現場で導入されていました。ただし、従来、企業は支援金を給与に上乗せする形で給付し、返還はあくまで従業員各人が行う方法のみに限られていました。
日本学生支援機構は2021年4月に「奨学金返還支援制度」を新設し、貸与元である機構に対して企業が直接返還額を送金できるようになりました。
企業が「奨学金返還支援(代理返還)制度」を活用するためには、機構に対して、事前の利用申請や返還額の送金等に対応する必要があり、こうした事務処理を負担に感じる現場もあるでしょう。もちろん、これまで通り、支援額を従業員の給与に上乗せする形で支援することも可能ですが、「奨学金返還支援(代理返還)制度」活用のポイントを踏まえた上で検討するのが得策です。
奨学金返還支援(代理返還)制度活用のポイント① 実質的な手取り額向上
企業の奨学金返還支援については、所得税と社会保険料の算定時に特別な取り扱いがなされます。これにより、従業員給与の手取り額を向上させることができます。
所得税
国税庁によると、「奨学金の返済に充てるための給付は、その奨学金が学資に充てられており、かつ、その給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、課税の適正性、公平性を損なうものではない」とされ、つまりは一定の要件を満たす奨学金返還支援は所得税の非課税対象とすることができます。
この点、支援額を給与に上乗せする形での従来型の支援では、従業員が受けた支援額が奨学金の返済に充てられるかについては疑義があり、厳密には「学資に充てられた」とみなせず、結果的に所得税の課税対象となります。一方で、企業が直接機構に返還額を送金することで、従業員の通常の給与と 返還額が明確に区分されることになりますので、その返還額に関しては 所得税の非課税扱いとすることができます。
社会保険料
日本年金機構によると「奨学金返還支援(代理返還)を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから標準報酬月額の算定の元となる報酬等に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため報酬等に該当する。」とのことです。
奨学金返還支援(代理返還)制度活用のポイント② 税制上の優遇を享受
奨学金返還支援(代理返還)は従業員の奨学金の返済に充てるための給付に該当するため、給与として損金算入が可能となり、法人税の課税所得を圧縮できます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。「賃上げ促進税制」に関する詳細は、以下より確認いただけます。
参考:中小企業庁「中小企業向け「賃上げ促進税制」」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
奨学金返還支援(代理返還)制度活用のポイント③ 採用活動時の差別化に貢献
実に学生の3人に1人が奨学金を活用する状況下において、従業員の奨学金返還支援制度を有する企業は、就職活動中の学生から高い注目を得ることができるでしょう。奨学金返還支援(代理返還)制度を利用する企業は、日本学生支援機構のホームページにおいてその企業名が公表される他、同ホームページでは求職者側は地域や業種で企業を検索することができるようになっているため、同業他社と差別化につながります。
奨学金返還支援(代理返還)制度活用の留意点を確認
一方で、奨学金返還支援(代理返還)制度を活用する上では、留意すべき点もあります。
税制上の優遇等には一部例外あり
例えば、対象者が役員である場合、報酬が損金不算入となる他、所得税の課税対象となることがあります。また、返還額は原則、社会保険料算定上の「報酬等」に含まれませんが、給与規程等で「給与に代えて奨学金返還を行う」旨が規定されている場合には返還額部分も社会保険料の算定基礎に含まれます。
もちろん、社会保険料に関しては支払った分、将来の年金給付等に反映されるため、一概に「社会保険料を抑えるのが良い」とは言えませんが、奨学金返還を抱える従業員は現在の手取り額を重視する傾向にあります。対象者や社内規程等について、あらかじめ専門家に相談いただいた上での制度導入がお勧めです。
従業員に支援金の返還を求めることはできません
企業による奨学金返還支援は、民法上の代位弁済とは異なり、あくまで福利厚生の一環となります。そのため、企業が従業員に代わって奨学金を返還しても、後になって従業員に対してその返還額を求めることができません。例えば、社内規程で「3年以内に退職した場合は、支援額を全額返還しなければならない」等のルールを設けたとしても無効となります。
せっかくの制度導入も、従業員間の不公平感の増幅につながる可能性があります
どのような福利厚生制度を導入する場合にも、恩恵を受けられる人と受けられない人との間には実質的な格差が生じることになります。これに起因する従業員間の不公平感は、奨学金返還支援に限ったことではなく、家族手当や住宅手当、育児や介護に関わる支援等においてもしばしば問題となります。
とりわけ、奨学金返還支援のような特定の従業員向けの制度を導入するに際しては、全従業員に対してあらかじめ導入の理由や目的を丁寧に説明した上で、理解を得られる様に努める必要があります。
若手人材の確保・定着に向けた好影響が期待される奨学金返還支援制度ですが、導入によって想定される既存人材のモチベーション・エンゲージメントへの悪影響も十分に考慮した上で、慎重に制度導入を進めていく必要があります。
導入の目的を明確にし、貴社に活きる奨学金返還支援(代理返還)制度の創設を
企業における奨学金返還支援制度は、福利厚生の一種であるため、各現場で自由度の高い制度設計が可能です。導入事例では、若手人材を対象に概ね3年~10年の一定期間支援する内容を中心に、支援対象を新卒者に限定する、特定の職種に従事する従業員のみを対象とする、在職期間中はずっと支援対象とする、勤続年数に応じて支援を手厚くする等、様々な制度が見受けられます。
これから奨学金返還支援制度を導入する企業においては、「他社事例を参考に、同じような制度を導入してみる」というやり方も試験的には良いかもしれませんが、できれば人事課題に鑑み、どのような目的で制度を導入するのかを十分に検討した上で、自社の人事戦略において「活きる制度」の設計ができるのが理想です。

丸山博美(社会保険労務士)
社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。
丸山博美(社会保険労務士) の記事一覧







