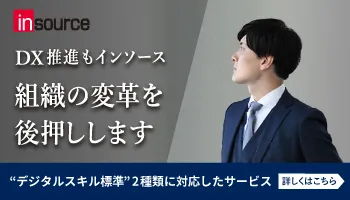Z世代と呼ばれる今年の新入社員は漠然とした不安を抱えている。
ALL DIFFERENT(旧ラーニングエージェンシー)が実施した「働くことに関する新入社員意識調査レポート」(2023年4月19日)によると、入社式を終えた新入社員の現在の気持ちを聞くと、「不安」が34.8%、「緊張」が21.7%もあり、「期待」は14.9%にすぎない(単一選択)。どんなことに不安を感じているのか。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)
Z世代は上下関係が苦手
「仕事についていけるか(仕事の難易度)」が64.9%と最も多く、次いで「生活リズムや社会人としての考え方の習得」(45.9%)、「社会人の基礎的なマナーの習得」(41.0%)と続く。こうした不安感の背景にはあるのは対人コミュニケーションの少なさにあると思われる。
Z世代は最初に手にした携帯がスマホであり、情報収集やコミュニケーションの手段としてインターネットやSNSを駆使する。
しかしその一方で、SNSを通じて小・中・高・大学の横のつながりは広いが、上下の人間関係のコミュニケーションに不得手な人も多いと言われる。 しかも大学時代はコロナ禍で対面のコミュニケーションが極端に減った。
Z世代が求めるのは丁寧で優しい上司
仕事に対する不安感の表れだろうか。
「自分のキャリアアップにつながる理想の上司」について聞くと「間違いを指摘して正してくれる上司」と回答した割合が最も多く57.4%、次いで「自分のことをよく見てくれ、声をかけてくれる」(41.1%)、「具体的に手順を細かく教えてくれる」(40.9%)と続く。
要するに丁寧に指導してくれる優しい上司である。
Z世代が丁寧で優しい上司を求めるのがよくわかると語るのは広告関連業の人事課長だ。
「最近の新入社員は教科書通りにやることはすごく得意だし、ある意味で優秀だと思うが、ただし共通するのは、失敗を恐れる優等生という感じだ」
「先輩や上司がちゃんと教えてくれないことに不満を抱え、教えてもらっていないことをやることを極端に嫌がる傾向がある。何かミスをして叱っても『教えてもらっていませんから』と平気で言う」 「それでいて相手の懐に飛び込んで、教えを請うのが苦手だ。へりくだって教えてくださいと言うのが嫌だし、教えてくれないのも嫌なのである」
丁寧で優しい上司は聞き上手
新入社員が理想とする「丁寧でやさしく指導してくれる上司」は多いのか。
建設会社の人事課長は、「丁寧で優しく指導してくれる上司の最大の特徴は、何より聞き上手であること。じっくり話を聞き、与えた仕事が本人のキャリアのために必要であることをわかりやすく丁寧に説明し、目指すべきゴールを設定してあげる」
「たとえば『今はムダな仕事だと思っているかもしれないが、いずれきっと役に立つから』、あるいは『今は大変かもしれないが、だからこそ君にやらせるんだ』と、本人の意欲を奮い立たせるのが非常にうまい人だ」 「ただし、言葉で言えば簡単だが、それを実行できる管理職は少ない」と語る。

Z世代は人並みに安定した生活を望む
仕事に対する向き合い方にも特徴がある。「仕事を通じて成し遂げたいこと」の質問の回答で最も多かったのは「安定した生活を送りたい」であり、65.8%だった(複数回答)。
この割合は過去最大であり、2019年以降、4年連続で増加している。
2番目に多かったのは「自分を成長させたい」で、57.8%。こちらは2020年までは増加傾向にあったが、その後は減少し続けている。
安定した生活といっても大金を稼ぎたいわけではなく、「大金を稼ぎたい」と回答した人は20.8%にすぎない。 人並みの生活ができる程度の収入を安定的に得たいというささやかな希望である。
出世意欲は低く、転職志向が強い
ただ、会社人生において安定した生活を送るには昇進し、収入を上げることが必要になるが、出世志向は低い。
キャリタスリサーチが2023年春に大学・大学院を卒業する学生を対象に調査した「キャリアプラン・ライフプランに関する調査」(2023年3月)によると、「出世したいとは思わない」男性が7.0%、女性が20.0%、「特に考えていない」は男性が29.8%、女性は38.4%もいる。
出世については無関心の人が少なくない。
一方で転職志向が強い。入社する企業の勤務予定期間では10年以内の回答は、男性が48.5%、女性が53.3%も存在し、半分以上転職を意識している。
出世する、管理職になることは、会社という組織を代表することであり、会社への信頼感や帰属意識を意味する。
しかし、この世代は会社への信頼感や帰属意識は少なく、転職も選択肢であると考えている。
前出の調査で2番目に多かった「自分を成長させたい」と思っている。また、「どのような仕事をしていきたいか」という質問で2番目に多かったのが「自身の成長につながる仕事」(48.2%)と答えている。 会社や組織の成長よりも自身の成長を重視し、転職しても世間に通用するスキルを身につけたいという志向が強いのであろう。
企業に育成力が試される
これは「安定した生活を送りたい」ことと矛盾しない。安定した生活とは、会社に守られる生活ではない。
一つの会社に依存し、定年まで勤めることは幻想にすぎず、むしろリスクでもあると捉え、個人としてサバイブしていくしかないと考えている。
ということは「自身の成長につながらない」、「上司が丁寧に教えてくれない」となると、退職するリスクも高くなる。 このような新人の志向や価値観に応じた指導や育成をどうしていくのか。企業の育成力が試されている。