多くの企業が人材を奪い合う状況となり、これまでの人事制度のままでは人材の確保が難しくなっている。企業の人材マネジメントを支援している専門家に、人材戦略の見直しに向けた課題や取り組みなどを聞いた。(編集:日本人材ニュース編集部)

エンプラス
湯浅雄介 代表取締役社長

外国人社員雇用の基礎知識を学び、制度設計や規程等を整備
国内の労働人口減少が今後さらに進むことが想定され、グローバル人材の活躍が不可欠となる一方、多くの企業では外国人受け入れに関する社内体制や手続き面の整備が遅れています。
就労資格の取得や住民登録などの法的な対応に加え、言語・文化への配慮、社内理解の醸成など、受け入れ企業としては多層的な対応が必要となるため、まずは人事部門などが主導し、外国人社員の雇用における基礎知識を学び、制度設計や規程等を整えていくことが求められます。加えて、外国人材の定着を図っていくためには、入社後のオンボーディング支援、相談体制の構築が重要となります。
当社は外国人社員が安心して働き、暮らせる環境づくりを、住まいや生活面から創業20年にわたり支援しています。
エル・ティー・エス
青地忠浩 経営革新・ヒューマノクラシー推進事業部 シニアマネージャー・部長代行

職場の組織開発やミドルマネジメント層の意識・行動変容が重要
人材戦略の見直しで重要なのは、長期経営ビジョンとの連動性、事業部門・現場の納得感、個人と組織のウェルビーイングです。多くの企業がDXに取り組んでいますが、よく聞くのは「せっかく変革人財を育てても、スキルを活かす機会と周囲のサポートがなく孤立している」、「人事評価やキャリアモデル、組織カルチャーがマッチしておらず、モチベーションの低下・離職に繋がっている」といった声です。
当社では、創出したい価値を基点に、「人財・組織能力」、「組織カルチャー」、「組織体制・制度」といった組織要素との一貫性のある人材戦略の策定と取り組みを支援しています。今後は、変革人財を継続的に輩出していくための能力開発に加え、職場の組織開発やミドルマネジメント層の意識・行動変容が重要となるでしょう。
Luvir Consulting
岡田幸士 共同経営者 /COO

中長期的な「経営戦略」起点でシビアに必要な人の量・質を検討
「現場の意見を聞きすぎないこと」が人材戦略の見直しにおいては重要です。人材戦略とは「経営戦略を実現するための人材の量・質」を定義するものです。特に人材の充足は1~2年スパンでは困難であり、基本的には3~5年以上先を見据えて策定すべきです。
しかし、多くの企業では、現場において“いま不足している人材”に焦点が当たりがちです。なおかつ現場においては、人員数を減らすことなど、“変化”に対する抵抗を示すことも多分にあります。もちろん、現場の課題やニーズを一定拾うことも重要ですが、あくまで中長期的な「経営戦略」を起点にして、シビアに必要な人の量・質を検討していくことが、人材戦略の効果を高める上では重要になるのです。
エンファクトリー
加藤健太 代表取締役社長 CEO 兼 CHCO
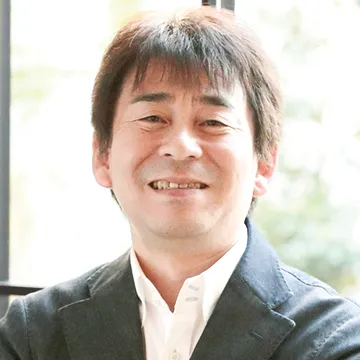
社外の経営層と実践を行う越境学習で次世代リーダーを育成
変化の激しいビジネス環境に適応できる次世代リーダーの育成が喫緊の課題です。「座学だけでは経営の実践力が養えない」といった課題に対し、従来の経営塾に組み合わせ「タフアサインメントの場」を、社外のそれも経営層の近くで実践を行う企業が増えてきています。
例えば、キヤノンマーケティングジャパンでは未来を担う経営リーダー育成のため越境学習を導入し、ベンチャー企業の経営者との実践を通じた「ストレッチ経験」を提供し、アセスメントにも活用しています。大企業ほど、次世代リーダーに必要な経営に触れる機会を社内ですぐに用意することは難しく、社外での「場のデザイン」という考え方をぜひ取り入れてみてください。
WizWe
津野大紀 執行役員 /HRプラットフォーム カンパニー カンパニー長

スキルの棚卸しと測定、適切な研修設計・実施で語学力を高める
米関税強化・米中対立の激化と生成AIの台頭で、語学を武器に世界の情報と市場を即時に捉える人材が企業価値を左右。実務能力は高いが語学力が低い層の育成が課題です。また、人的資本開示の流れの中で育成投資の費用対効果や事業成果との接続についての可視化も課題となってきます。
解決策としては、タレントマネジメントツールやLMSなどの導入で、必要なスキルの棚卸しと測定を行うこと。そして、適切な研修設計・実施により役職員のスキル向上を図ることが王道です。ただし、研修設計・実施まで落とし込んでも、役職員が現場で多忙すぎて能力向上に時間を割けないといった課題が浮上することが多く、当社では語学研修を中心に、伴走サポートによる研修成果最大化を提供しています。
パーソル総合研究所
藤井薫 上席主任研究員

専門性開発・処遇見直しでミドル・シニアが活躍できる環境を作る
人材不足が深刻化する中、黒字リストラが相次ぐなど、企業はミドル・シニアを十分に活用できていない状況です。少子高齢化や雇用長期化の影響で、従業員に占めるミドル・シニアの割合はさらなる増加が見込まれます。ミドル・シニアが能力を発揮して活躍できる環境を作ることは喫緊の課題です。
管理職はポジション数が限られており、組織活性化の観点からは適度な新陳代謝が欠かせません。管理職の大半は、いずれプレーヤーに戻ることになります。一方、高度専門職の人数は企業の人材の層の厚さに直結し、中高齢でも十分な活躍余地があります。専門性開発のあり方は人材戦略の核になります。また、モチベーションの観点からは、ミドル・シニア処遇のあり方を抜本的に見直す必要がありそうです。
日本マンパワー
依田哲司 HR法人ソリューション本部 コンサルティング部 担当部長

支援型マネジャーへ転換を図り、社員と組織の共成長を目指す
人材戦略の見直しに向けた課題という点で、ハードとソフト、両面から相談を受けるケースが増えています。ハード面では経営戦略との整合性、経営目標に連動したキャリアマップやスキルマップ、ラーニングマップの設計相談が多く、その構築により、会社の向かう方向と、社員の“なりたい姿”を連動させることで、人材定着やエンゲージメント向上も狙っています。
ソフト面では、管理職のマインドリセット。管理型マネジャーから支援型マネジャーへと転換を図りたいという相談が増えており、導入から浸透まで、「1on1」を中心施策に据えながら、社員と組織の共成長を目指しています。なお、運用基盤にタレントマネジメントシステムを入れる企業が多いですが、運用思想や目的が曖昧なケースが多いので注意が必要です。
タナベコンサルティング
川島克也 取締役 HRコンサルティング事業部担当

人材マネジメントの KGI・KPIを設定し、成果をモニタリング
当社調査では、長期ビジョン・中期経営計画を策定している企業のうち6割以上が「具体的な戦略が不足している」という結果でした。昨今注目されている人的資本経営の実装に向けても取り組めていない企業が多いのが実情です。
具体的な取り組み例としては、人材マネジメントの成果をKGI・KPIとして設定し、モニタリングを行う仕組みを組織に備えることが挙げられます。その中で、特に重要な指標が「一人あたりの生産性」と「エンゲージメント」です。人材戦略の推進でどれだけ生産性が向上しているのか、持続的にパフォーマンスを発揮できるのかを検証し、対策を講じていく必要があります。
そうした中で、人材戦略を推進する機能として、CHROの設置やHRBP機能の強化といった人事部門改革への取り組みも重要課題です。






