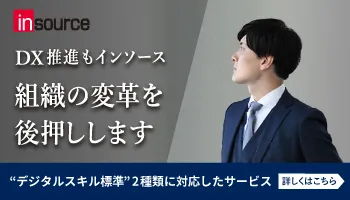政府の「新しい資本主義実現会議」(議長・岸田文雄首相)が打ち出した「三位一体の労働市場改革の指針」が話題を呼んでいる。指針は骨太の方針にも盛り込まれ、いわゆる“退職金増税”も含まれるなど、今後の雇用・労働政策を大きく左右するものとなっている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)
個人はリスキリング、企業はジョブ型で転職を容易にし、賃金上昇を目指す
指針の内容は「リスキリングによる能力向上支援」、「企業の実態に応じた職務給の導入」、「成長分野への労働移動の円滑化」の三位一体の労働市場改革を行い、構造的に賃金が上昇する仕組みを作っていくのが狙いだ。
指針は、まず基本的考え方として「キャリアは会社から与えられるもの」から「一人ひとりが自らのキャリアを選択する」時代になってきたと述べた後、今後の方向性についてこう述べている。
「職務ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリスキリングを行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である。そうすることにより、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用にも門戸を開き、労働者が自らの選択によって、社内・社外共に労働移動できるようにしていくことが、日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務である」。
個人に対しては時代が求めるスキルを習得するリスキリングを支援し、企業に対しては求めるスキルを明確にした職務給というジョブ型賃金の導入を促し、転職が容易になるようにして賃金が上がっていく仕組みをつくっていくというものだ。
リスキリング・ジョブ型・転職についての具体的政策とは
具体的政策を見てみよう。リスキリングによる能力向上支援策としては、現在、企業経由の支援策が75%(771億円)を占め、個人経由が25%(237億円)を占めている構造を改め、企業に在職している個人が主体的に選択できるように5年以内を目途に予算の「過半」が個人経由での給付が可能となるようにするとしている。
また、個人が習得したスキルの履歴の可視化を可能とする一助として、デジタル上での資格情報の認証・表示の仕組み(オープンバッジ)の活用を推奨する。さらにデジタル分野へのリスキリングを強化するため、専門実践教育訓練について、デジタル関係講座数を2025年度末までに300講座以上(現在179講座)に拡大する。
2番目の企業の実態に応じた職務給(ジョブ型人事)の導入では、職務給の必要性について、戦後に形成された年功賃金制などの雇用システムを批判し、こう述べる。
「職務(ジョブ)やこれに要求されるスキルの基準も不明瞭なため、評価・賃金の客観性と透明性が十分確保されておらず、個人がどう頑張ったら報われるかが分かりにくいため、エンゲージメントが低いことに加え、転職しにくく、転職したとしても給料アップにつながりにくかった」。
その上で「職務給の個々の企業の実態に合った導入等による構造的賃上げを通じ、同じ職務であるにもかかわらず、日本企業と外国企業の間に存在する賃金格差を、国ごとの経済事情の差を勘案しつつ、縮小することを目指す」としている。
そして職務給導入の推進策として、今年度内に、職務給の日本企業の人材確保の上での目的、ジョブの整理・括り方、これらに基づく人材の配置・育成・評価方法、ポスティング(公募)制度、リスキリングの方法、従業員のパフォーマンス改善計画(PIP)、賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係、休暇制度などについて、事例を整理し、個々の企業が制度の導入を行うために参考となるよう、多様なモデルを示すとしている。
3番目の成長分野への労働移動の円滑化の施策としては、自己都合で離職する場合、求職申込後2カ月ないし3カ月は失業給付を受給できない失業給付制度を見直し、失業給付の申請時点から遡って例えば1年以内にリスキリングに取り組んでいた場合などについて会社都合の場合と同じ扱いとするなど、自己都合の場合の要件を緩和する方向で具体的検討を行うとしている。
勤続28年、退職金2000万円の場合、新たに約15万円の課税となる可能性

そして問題となった退職所得課税の見直しについてはこう述べる。
「勤続20年を境に、勤続1年あたりの控除額が40万円から70万円に増額される。これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘があり、制度変更に伴う影響に留意しつつ、本税制の見直しを行う」。
つまり、退職金の所得控除が長期勤続者ほど優遇されている現行制度が転職を阻害しているという理屈である。現行の退職金から控除される退職所得控除額は以下の計算式になる。
勤続20年以下 40万円×勤続年数勤続20年超
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
確かに勤続20年の人は800万円しか控除されないが、21年目になると、控除額が40万円から70万円に増額される。
仮に定年退職金を2000万円としよう。現行の基準で大卒入社後38年で定年を迎えるとして計算すると、退職所得控除額は、
800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円
となり、税金はかからない。 しかし、20年以下と同じ計算式では、退職所得控除額は、
40万円×38年=1520万円になる。
課税退職所得額は、所得控除額を差し引いた金額の2分1であり、(2000万円-1520万円)÷2=240万円。
これにかかる所得税は、240万円×税率10%-控除額9万7500円=14万2500円となる。
これに復興特別所得税を加えると約15万円の税金がかかる。
勤続20年以下の退職所得控除額と同じになると、平均的なサラリーマンの退職金に15万円課税されることになる。
三位一体の概要について、現時点での実現性は未知数
以上が三位一体の改革の概要であるが、指針の内容について労使が全面的に賛成しているわけではない。新しい資本主義実現会議の委員でもある十倉雅和経団連会長は、職務給導入については、導入の目的や方法などは各社の実情に応じて異なるとし、「年内に取りまとめる事例集は、あくまで各企業が自社の実情に応じて主体的に導入を検討する際に参考とするものにしていただきたい」と、注文をつけた(「第18回新しい資本主義実現会議議事要旨」以下同じ)。
また同委員の芳野友子連合会長は、職務給の導入について「企業の人事制度は産業を取り巻く情勢、労使慣行や職場実態に即して、労使が主体的に検討すべきである」とした上で、導入について「企業規模や業種によってなじまない場合があることからも、慎重な検討が必要である」と、職務給導入推進に慎重な姿勢を見せた。
職務給の導入について、連合の幹部は「政府の中でも職務給の考え方が全然違う。業界横断的な職務給を作るという人もいれば、日本型職務給だからそんなことは考えていないという人もいる。正直言ってそんなに大きな動きにならないのではないか」と語る。
また、現場の工場などで働く技能職については「経営者のほとんどは導入することは考えていない」と語り、こう言う。
「職務給の導入によって、従業員の賃金が固定され、上がらなくなると思った瞬間に、労働組合は反対せざるを得なくなるかもしれない」。
三位一体の改革によって賃金が上がるかどうか以前に、改革そのものの実現性が現段階では未知数といえる。